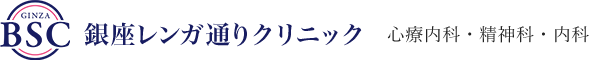- 2025年10月9日
- 2025年10月5日
5,過活動膀胱と合併しやすい病気:もしかしたら隠れた原因があるかも?
「トイレが近いのは、過活動膀胱だけが原因じゃないって本当?」そう疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれません。過活動膀胱は、それ自体が独立した病気として診断されることが多いですが、実は、他の病気が原因で発症したり、あるいは他の病気と同時に起こりやすかったりすることがあります。これらの合併しやすい病気を知ることは、あなたの症状の根本原因を理解し、より適切な治療へと繋がる大切なステップとなります。
過活動膀胱の背景に潜む可能性のある病気
過活動膀胱は、膀胱の神経や筋肉の異常によって起こりますが、その異常が別の病気によって引き起こされているケースも少なくありません。
- 男性における前立腺肥大症: 男性の場合、加齢とともに前立腺が肥大し、尿道を圧迫することがあります。これにより、尿の勢いが弱くなったり、排尿に時間がかかったり、排尿後に尿が残る(残尿)といった症状が出ます。膀胱は、この排尿障害に抵抗して無理に尿を出そうとすることで、結果的に過敏になり、過活動膀胱の症状を合併することが非常に多いです。前立腺肥大症の治療を行うことで、過活動膀胱の症状も改善することが期待できます。
- 神経疾患: 脳や脊髄などの神経に異常があると、膀胱と脳との間の神経伝達がうまくいかなくなり、膀胱が勝手に収縮してしまうことがあります。これを「神経因性膀胱」と呼び、過活動膀胱はその一種として現れることがあります。
- 脳血管障害(脳梗塞、脳出血など): 脳の排尿をコントロールする部分に損傷があると、過活動膀胱を引き起こすことがあります。
- パーキンソン病: 脳の神経変性疾患で、排尿コントロールにも影響が出ることがあります。
- 脊髄損傷、多発性硬化症: 脊髄の損傷や疾患も、膀胱の神経伝達を妨げ、過活動膀胱の原因となります。
- 糖尿病: 糖尿病が長期間続くと、高血糖によって全身の神経に障害が起こることがあります(糖尿病性神経障害)。膀胱を支配する神経も影響を受け、膀胱の感覚が鈍くなる「神経因性膀胱」や、逆に膀胱が過敏になる過活動膀胱の症状を合併することがあります。
- 膀胱炎や尿路感染症: 膀胱炎やその他の尿路感染症は、膀胱に炎症を起こし、尿意切迫感や頻尿、排尿時痛などの症状を引き起こします。感染症が治癒した後も、膀胱の過敏性が残って過活動膀胱の症状が続くことがあります。
- 膀胱がん: 稀ではありますが、膀胱がんが膀胱を刺激し、尿意切迫感や頻尿、血尿などの症状を引き起こすことがあります。特に、これまでの排尿症状とは異なる、突然の症状変化があった場合には注意が必要です。
合併症を考慮した総合的な診断と治療の重要性
このように、過活動膀胱の症状の裏には、別の病気が隠れている可能性があります。そのため、単に過活動膀胱として治療するだけでなく、これらの合併しやすい病気の有無をきちんと確認することが、正確な診断と効果的な治療を行う上で非常に重要です。
- 問診の徹底: 医師は、排尿に関する症状だけでなく、既往歴、服用中の薬、他の体の不調など、全身の状態について詳しくお伺いします。
- 必要な検査の実施: 尿検査で感染症の有無を調べたり、男性であれば前立腺の状態を確認したり、必要に応じて血液検査や神経学的検査などを行うこともあります。
当クリニックでは、患者さんの排尿の悩みに真摯に耳を傾け、単に症状を抑えるだけでなく、その背景にある可能性のある病気も考慮した総合的な診断を行います。そして、一人ひとりの状態に合わせた最適な治療計画を提案し、安心してより快適な生活を送れるよう、全力でサポートさせていただきます。