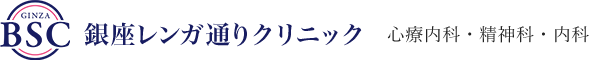- 2025年10月6日
- 2025年10月5日
2,なぜ過活動膀胱になるの?原因と発症のメカニズムを解説
「トイレが近いのは、年のせいだから仕方ない」「冷え性だからかな」。過活動膀胱の症状に悩む多くの方が、漠然とそう考えているかもしれません。しかし、過活動膀胱は加齢だけでなく、様々な要因が複雑に絡み合って発症する病気です。その原因とメカニズムを理解することで、症状への不安が和らぎ、適切な治療への意識が高まります。
膀胱の「誤作動」が主な原因
過活動膀胱の最も中心的な原因は、膀胱が尿を十分に溜めきれていないのに、**勝手に収縮しようとする「排尿筋の過活動」**です。通常、膀胱は尿が溜まると徐々に伸びて、ある程度の量になるまで尿意を感じないようにできています。しかし、過活動膀胱では、この膀胱が少し尿が溜まっただけで敏感に反応し、収縮しようとすることで、急な強い尿意(尿意切迫感)を引き起こします。
この排尿筋の過活動は、さらにいくつかの要因によって引き起こされると考えられています。
- 脳と膀胱の神経伝達の異常: 膀胱が尿で満たされていく情報は、神経を通じて脳に伝えられ、脳が排尿のタイミングをコントロールしています。しかし、この神経伝達の経路に異常が生じると、膀胱が「まだ尿を溜められる」という信号を正確に受け取れず、早すぎるタイミングで「もういっぱいだ、排尿しろ」という指令を出してしまうことがあります。
- 脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)、パーキンソン病、脊髄損傷などの神経疾患が原因で、脳と膀胱の連携がうまくいかなくなる「神経因性膀胱」の一種として過活動膀胱の症状が出ることがあります。
- 神経系だけでなく、自律神経の乱れも膀胱の働きに影響を与え、過敏に反応しやすくする可能性があります。
- 膀胱の過敏性: 何らかの原因で膀胱自体が過敏な状態になり、少量の尿でも強い尿意を感じてしまうことがあります。膀胱の炎症(膀胱炎など)が治った後も過敏性が残ったり、カフェインや刺激物の過剰摂取が膀胱を刺激したりすることも、一時的に過敏性を高める原因となることがあります。
年齢や性別、生活習慣との関連性
過活動膀胱は、以下のような要因によって発症リスクが高まると考えられています。
- 加齢: 男女ともに加齢とともに過活動膀胱の有病率は高まります。年齢を重ねるにつれて、膀胱や神経の機能が低下したり、生活習慣病を抱えたりすることが関係していると考えられます。
- 骨盤底筋の弱化: 特に女性の場合、出産や加齢によって骨盤底筋(膀胱や尿道を支える筋肉群)が弱くなると、膀胱や尿道の安定性が損なわれ、尿意切迫感や切迫性尿失禁のリスクが高まります。
- 男性の前立腺肥大症: 男性の場合、前立腺肥大症によって尿道が圧迫され、尿が出しにくくなることで、膀胱が無理に排尿しようと過剰に働くようになり、過活動膀胱の症状を合併することがよくあります。
- 生活習慣病:糖尿病による神経障害や、高血圧など、全身の血管や神経に影響を与える生活習慣病も、膀胱機能に影響を与える可能性があります。
- ストレス: 精神的なストレスは、自律神経のバランスを乱し、膀胱の働きにも影響を与えることがあります。不安や緊張が強いと、尿意を感じやすくなることもあります。
このように、過活動膀胱は単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症する病気です。ご自身の症状の原因を理解することで、より適切な治療法を選択し、改善への道を歩むことができるでしょう。
当クリニックでは、患者様一人ひとりの背景にある原因を探りながら、最適な治療計画をご提案いたします。トイレの悩みから解放され、安心して過ごせる毎日を取り戻しましょう。