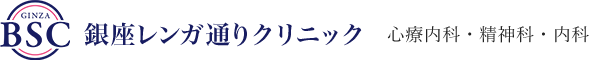- 2025年8月8日
- 2025年8月4日
5. 「治したい」を叶える!書痙の診断と治療の選択肢
「この手の震え、どうにかしたい」「どこに相談すればいいのか分からない」。書痙の症状に悩む多くの方が、そう願いながらも、なかなか一歩を踏み出せずにいます。書痙は、適切な診断と治療を受けることで、症状の改善が十分に期待できる疾患です。あなたは一人ではありません。安心して頼れる場所は必ずあります。
どこで相談できる?書痙の診断機関
書痙の診断は、主に以下の医療機関で行われます。
- 神経内科:
- 書痙は、脳の機能的な問題(局所性ジストニア)が背景にあると考えられているため、神経内科が診断・治療の中心となります。
- 他の神経疾患(本態性振戦など)との鑑別診断も行います。
- 精神科・心療内科:
- 書痙は、精神的な要因(予期不安、ストレスなど)が症状に大きく影響するため、精神科や心療内科も有効な相談先です。
- 精神的なアプローチ(カウンセリング、抗不安薬の処方など)から治療を行うことができます。
- 心身医療科、神経科など:
- 病院によっては、心と体の両面を診る専門科がある場合もあります。
ポイント: まずはかかりつけ医に相談し、必要に応じて上記の専門科を紹介してもらうのがスムーズです。症状を具体的に伝え、どのような場面で、どんな症状が出るのかを詳しく説明しましょう。
書痙の主な治療選択肢
書痙の治療は、患者さんの症状のタイプ、重症度、原因、ライフスタイルに合わせて、様々な方法が組み合わせて行われます。
- 薬物療法:
- βブロッカー: 緊張による震えを抑える効果が期待できます。高血圧の治療薬としても用いられますが、心臓の拍動を抑えることで、震えを軽減します。
- 抗不安薬: 予期不安が強い場合や、精神的な緊張を和らげるために用いられます。ただし、依存性や眠気などの副作用に注意が必要です。
- 抗コリン薬: 局所性ジストニアに用いられることがありますが、口渇、便秘、眠気などの副作用が出やすい場合があります。
- その他: ドーパミン作動薬など、ジストニアに用いられる薬が検討されることもあります。
- ボツリヌス療法(ボトックス治療):
- 痙性型(こわばりや痙攣が強いタイプ)の書痙に非常に有効な治療法です。
- 症状の原因となっている特定の筋肉に、ボツリヌス菌が産生する毒素(ボツリヌストキシン)を注射します。この毒素は筋肉の過剰な収縮を抑え、こわばりや震えを軽減します。
- 効果は一時的(3~6ヶ月程度)ですが、繰り返し治療が可能です。神経内科で行われることが多いです。
- 精神療法・カウンセリング:
- 薬物療法と並行して、または軽度の場合に単独で行われることもあります。
- 認知行動療法: 「手が震えるはずだ」「失敗するに違いない」といったネガティブな思考パターンを特定し、より現実的で建設的な思考に変えていくアプローチです。予期不安の軽減に有効です。
- リラクセーション法: 筋弛緩法、呼吸法、自律訓練法などを学び、体の緊張を和らげ、不安をコントロールするスキルを身につけます。
- バイオフィードバック: 生体情報を測定器で可視化し、それを見ながらリラックス状態に導く練習をします。
- その他(作業療法、自助具など):
- 字を書く姿勢の改善、筆記具の選び方(太いペン、重いペンなど)、握り方の工夫など、作業療法士が指導することもあります。
- 症状に応じて、ペンを握りやすくする自助具の使用も検討されます。
「治したい」というあなたの気持ちは、回復への大きな原動力となります。書痙は、決して一人で抱え込む病気ではありません。どうぞ安心して、当院にご相談ください。私たちは、あなたが希望を取り戻し、自信を持って文字を書けるよう、全力でサポートさせていただきます。