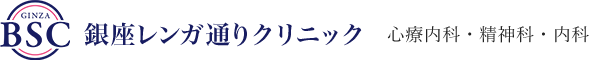- 2025年8月6日
- 2025年8月4日
3. 強迫性障害の診断:見えにくい苦しみに光を当てる
「この行動、おかしいとは思うけど、まさか病気だとは思わなかった」「病院に行くほどのことなのか…」。 強迫性障害は、その症状がご自身やご家族以外には見えにくいことが多く、また「性格だから」「考えすぎだ」と捉えられがちなため、診断が遅れてしまうケースが少なくありません。しかし、正確な診断は、適切な治療へと繋がり、回復への大切な一歩となります。
診断のポイント
強迫性障害の診断は、主に精神疾患の診断基準(DSM-5)に基づき、以下の点を総合的に評価して行われます。
- 強迫観念の存在:
- 繰り返し、持続的に出現する思考、衝動、イメージであり、ほとんどの場合、不快で、侵入的で、不適切であると感じられる。
- 患者がそれらを無視したり抑圧したり、他の思考や行動で中和しようと試みる。
- これらの思考、衝動、イメージが、単なる現実の問題に関する過剰な心配ではない。
- 強迫行為の存在:
- 強迫観念に反応して、または厳密に守られなければならない規則に従って行われる、反復的な行動(例:手洗い、整理整頓、確認)や精神的な行為(例:祈る、数える、言葉を心の中で繰り返す)。
- これらの行為は、不安を和らげたり、恐ろしい出来事を防いだりするために行われる。しかし、それらの行為は、現実的な方法でその出来事と結びついているわけではなく、明らかに過剰である。
- 時間的消耗と機能障害: 強迫観念や強迫行為に毎日1時間以上費やしている、または、これらの症状によって仕事、学業、社会生活、人間関係など、日常生活の重要な領域において、著しい苦痛や機能の障害が引き起こされていること。
- 他の精神疾患や物質の影響の除外: 症状が他の精神疾患(例:不安症、うつ病、摂食障害、チック症など)の症状の一部ではないこと、または薬物やアルコールの影響によるものではないこと。
- 病識の有無: 「自分の強迫観念や強迫行為が、過剰である、または不合理である」という認識(病識)があるのが典型的ですが、病識がほとんどない、または全くないケースもあります。
具体的な診断プロセス
- 詳細な問診: 医師は、現在の症状(どのような強迫観念・強迫行為があるか、いつから、どのくらいの頻度で、どんな時に起こるか、それらにどのくらい時間を費やしているかなど)、過去の病歴、家族歴、生活環境、ストレス要因などを詳しく聞き取ります。症状の具体的な内容や、日常生活への影響について正直に伝えることが重要です。
- 精神症状の評価: 抑うつ気分、不安、衝動性など、強迫性障害と関連する他の精神症状についても確認します。
- 身体診察・検査: 他の身体疾患が原因で症状が出ている可能性を除外するために、身体診察や血液検査が行われることがあります。
- 心理検査: 必要に応じて、強迫性障害の重症度を測る質問票(例:Y-BOCS)などを行うこともあります。
「病気だ」と知ることの意味 強迫性障害の診断を受けることは、決してあなたを「レッテル貼り」するものではありません。むしろ、あなたが長年苦しんできた「止められない苦しみ」に名前がつき、それが治療によって改善できる心の状態であると理解するための、大切な出発点となります。
「自分が病気だ」と受け入れることは、最初は抵抗があるかもしれません。しかし、診断があることで、あなたに合った適切な治療法が見つかり、回復への具体的な道筋が見えてきます。
もし、ご自身の思考や行動パターンに、上記のような心当たりがあり、苦しんでいるのであれば、一人で抱え込まず、専門の心療内科や精神科にご相談ください。私たちは、あなたの見えにくい苦しみに光を当て、正確な診断と、あなたに寄り添った治療を提供することで、回復へのサポートをいたします。