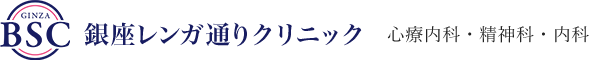- 2025年7月25日
- 2025年7月22日
4. 症状のコントロールが鍵!メニエール病の薬物療法と発作時の対処法
「突然のめまい発作が怖い…」「薬でメニエール病の症状は良くなるの?」。メニエール病と診断されたら、めまい発作や耳鳴り、難聴といった症状とどう向き合っていくかが重要になります。メニエール病を完全に治癒させる薬はまだありませんが、薬物療法によって症状をコントロールし、日常生活への影響を最小限に抑えることは十分に可能です。この記事では、メニエール病の主な薬物療法と、めまい発作が起こった際の適切な対処法について解説します。
メニエール病の薬物療法:内リンパ水腫の軽減と症状緩和
メニエール病の薬物療法は、大きく分けて「めまい発作時の急性期治療」と「発作予防のための維持期治療」があります。
1. めまい発作時の急性期治療: 強いめまい発作が起こった際に、症状を速やかに和らげることを目的とします。
- 制吐剤(せいとざい): 吐き気や嘔吐を抑える薬です。点滴で投与されることもあります。
- 抗めまい薬: めまいの症状を鎮める薬です。ジフェニドール、メクロジンなどがあります。
- 鎮静剤: 不安や動揺を抑え、精神的な安定を図る薬です。ジアゼパムなどがあります。
- ステロイド薬: 炎症を抑え、内リンパ水腫の軽減を目的として短期間使用されることがあります。
2. 発作予防のための維持期治療: 内リンパ水腫を軽減し、めまい発作の頻度や程度を減らすことを目的とします。継続的な服用が必要です。
- 利尿薬(りょにょうやく): 体内の余分な水分を排出し、内耳の内リンパ液の量を減らすことで内リンパ水腫を軽減します。イソソルビド(イソバイド®)やアデホスコーワ®などがよく用いられます。特にイソバイド®は、甘味があり飲みにくいと感じる方もいますが、効果が高いため指示通りに服用することが大切です。
- 循環改善薬: 内耳の血流を改善し、内耳の機能をサポートします。
- ビタミン剤: ビタミンB群などが内耳の神経機能の改善に用いられることがあります。
- 抗不安薬: ストレスや不安が誘因となる場合に、症状のコントロールを目的として少量用いられることがあります。
これらの薬は、患者さんの症状の程度、体質、合併症などを総合的に考慮し、耳鼻咽喉科専門医が慎重に判断して処方します。効果には個人差があり、全ての患者さんに劇的な効果が見られるわけではありませんが、発作の頻度を減らし、日常生活の質を保つ上で重要な役割を果たします。自己判断で服用を中止したり、量を変更したりしないようにしましょう。
めまい発作が起こった時の対処法:落ち着いて行動する
突然のめまい発作は、非常に不安で、動揺してしまうものです。しかし、慌てず落ち着いて行動することが、症状の悪化を防ぎ、安全を確保するために重要です。
- 安全な場所で横になる:
- めまいを感じたら、すぐに転倒の危険のない安全な場所を見つけ、横になりましょう。できれば、頭や首を動かさないように、楽な姿勢をとり、目を閉じると良いでしょう。
- 無理に起き上がろうとせず、めまいが落ち着くまでじっとしていましょう。
- 吐き気・嘔吐への対応:
- 吐き気がある場合は、顔を横向きにして、吐物が喉に詰まらないように注意しましょう。
- 可能であれば、吐き気止めの薬を服用しましょう。
- 安静にする:
- めまい発作中は、音や光の刺激が症状を悪化させることがあります。部屋を暗くし、静かな環境で安静にしましょう。
- 衣服を緩め、体を締め付けないようにしましょう。
- 無理に動かない: めまいが治まっても、急に起き上がったり、頭を動かしたりすると、再びめまいが誘発されることがあります。ゆっくりと体を起こし、しばらく座ってから立ち上がるようにしましょう。
- 水分補給: 嘔吐や冷や汗で脱水状態になることがあります。症状が落ち着いたら、少しずつ水分を補給しましょう。
- 外出先で発作が起きたら: 人目のある場所なら、周囲の人に助けを求めましょう。無理に移動せず、安全を確保できる場所で、症状が治まるのを待ちます。緊急の場合は、救急車を呼ぶことも検討しましょう。
- 発作を記録する: いつ、どこで、どんなめまいが、どれくらい続いたか、他にどんな症状があったか(耳鳴り、難聴、吐き気など)を記録しておくと、次の診察時に医師に伝える上で非常に役立ちます。
めまい発作は怖いものですが、適切な治療と冷静な対処でコントロールできることがほとんどです。発作時の対処法を事前に知っておくことで、いざという時にも落ち着いて対応できるようになります。当クリニックでは、薬物療法だけでなく、発作時の対処法についても丁寧に指導し、患者さんが安心して日常生活を送れるようサポートさせていただきます。