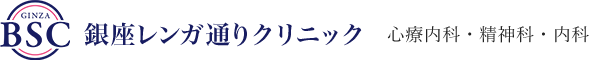- 2025年7月8日
- 2025年7月3日
6. 症状を和らげる薬はある?身体表現性障害の薬物療法Q&A
「身体の不調が辛いけれど、精神科の薬って抵抗があるな…」「どんな薬が使われるの?副作用は大丈夫?」。身体表現性障害(現:身体症状症)で悩む方が、薬物療法について不安や疑問を抱くのは当然のことです。身体表現性障害には、身体症状そのものを「完治させる特効薬」というものは存在しませんが、症状に伴う苦痛を和らげ、心身のバランスを整えるために薬が有効に用いられることがあります。
Q1. 身体表現性障害の治療で使われる薬にはどんな種類がありますか?
身体表現性障害の薬物療法は、主に身体症状に伴う精神症状や、その背景にある神経伝達物質のバランスの乱れを整えることを目的とします。
- 抗うつ薬(SSRI、SNRIなど):
- 最も頻繁に用いられる薬剤の一つです。
- 「抗うつ薬」という名称ですが、うつ病だけでなく、不安症状の軽減や、慢性的な痛みの軽減にも効果が期待できることがあります。脳内の神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリンなど)のバランスを整えることで、心身の安定を図ります。
- 効果が出るまでに時間がかかる(数週間~数ヶ月)ことがあります。
- 例: パロキセチン、セルトラリン、エスシタロプラム、デュロキセチンなど
- 抗不安薬:
- 強い不安感や緊張、不眠がある場合に、一時的に症状を和らげるために用いられます。
- 即効性がありますが、依存性や眠気などの副作用に注意が必要です。症状が安定したら、徐々に減量・中止を検討します。
- 例: エチゾラム、ロラゼパムなど
- 痛み止め:
- 痛みが主な症状である場合、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などの一般的な痛み止めが処方されることもありますが、効果は限定的であることが多いです。
- 慢性的な神経性の痛みには、抗うつ薬の一部(デュロキセチンなど)や、抗てんかん薬の一部(プレガバリンなど)が用いられることもあります。
- 漢方薬:
- 患者さんの体質や症状に合わせて、心身のバランスを整える目的で漢方薬が処方されることもあります。
- 例: 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)、加味逍遙散(かみしょうようさん)など
Q2. 薬の副作用が心配です。
どの薬にも副作用のリスクはありますが、医師は患者さんの状態を考慮し、副作用が最小限になるよう慎重に薬を選び、量を調整します。
- 一般的な副作用: 眠気、吐き気、口の渇き、便秘、めまいなどが挙げられます。
- 服用中に異常を感じたら: 自己判断で薬の量を減らしたり、服用を中止したりせず、必ず医師に相談してください。
Q3. 薬だけで身体表現性障害は完治しますか?
薬物療法は、身体表現性障害の症状に伴う苦痛を和らげ、精神状態を安定させるための重要なツールです。しかし、薬だけで症状が完全に「なくなる」完治を目指すのは難しい場合もあります。
- 補助的な役割: 薬は、身体症状そのものの原因を直接的に治すというよりは、症状を和らげ、精神的な負担を軽減し、他の治療法(精神療法など)に取り組むための土台を作る役割が大きいと言えます。
- 精神療法との併用: 薬物療法と並行して、認知行動療法などの精神療法、カウンセリング、生活習慣の改善などを行うことで、より高い治療効果が期待できます。これらの治療法は、症状の背景にある心理的な要因にアプローチし、再発を防ぐ上で非常に重要です。
Q4. 薬に依存することはありませんか?
抗不安薬には依存性がありますが、抗うつ薬や一般的な痛み止め、漢方薬には依存性はありません。医師は薬の種類や量を慎重に管理し、定期的に診察を行うことで、依存のリスクを最小限に抑えます。医師の指示に従って服用し、自己判断で中断しないことが重要です。
薬物療法は、身体表現性障害による苦痛を和らげ、日常生活を送りやすくするための有効な選択肢です。不安なことや疑問があれば、どうぞ一人で抱え込まず、当院にご相談ください。私たちは、あなたの症状や状況に合わせた最適な治療法を共に考えていきます。